AIO(AI最適化)とは?生成AI時代のWebサポート戦略
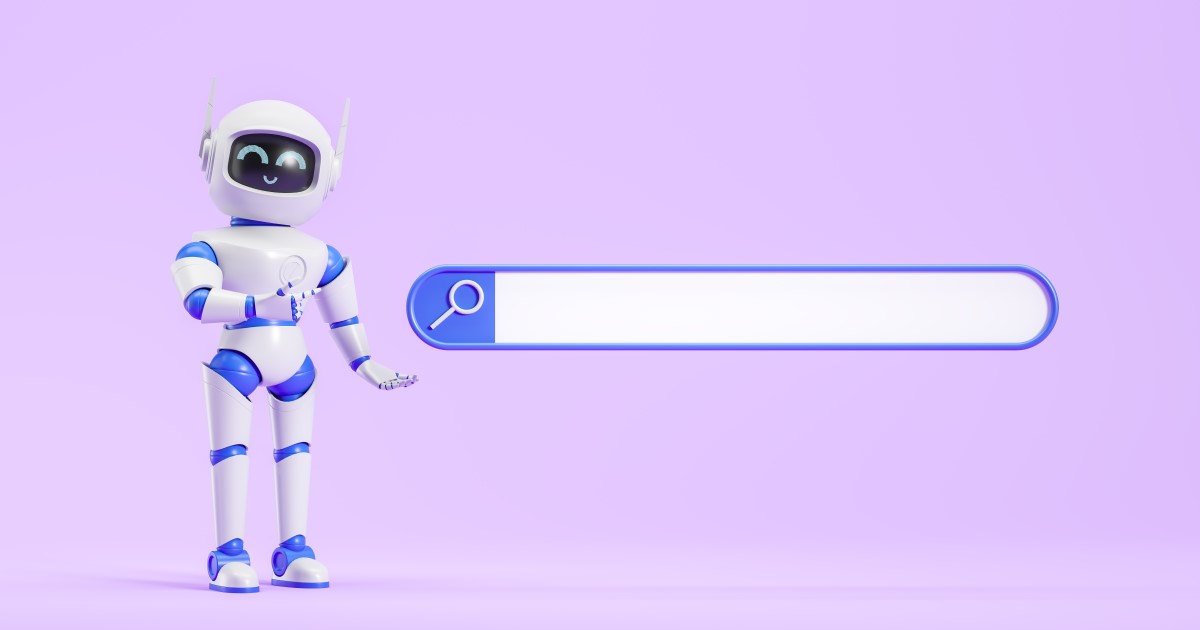
「AI検索で調べたら、うちのサービスが間違って紹介されていた」
そんな経験はありませんか?
生成AIの進化により、ユーザーはWebサイトを訪れる前にAIの回答で満足する時代になりました。
その中で重要性を増しているのが「AIO(AI最適化)」です。
本記事では、AIOとは何か、なぜ今注目されているのか、そしてWebサポートにおける実践的な対策について解説します。
AIO(AI最適化)とは?
AIO(AI最適化:Artificial Intelligence Optimization)とは、生成AIやAI検索エンジンに対して、自社の情報やコンテンツが正しく理解・引用されるように最適化する手法です。
これは、従来のSEO(検索エンジン最適化)と似た、新たなWebマーケティング戦略となっています。

一般的に、AIOはマーケティング界隈で使われ始めた概念です。
そのため、他の業界・職種では、馴染みが薄いです。



しかし実は、AIOは、顧客の問合せに対応するWebサポートでも、重要な要素です。
本記事では、サポート窓口視点を中心に、理由と対策を紹介します。
SEOとAIOの違い
| SEO | AIO | |
|---|---|---|
| 最適化対象 | ・検索エンジン (Google, Yahoo, Bing 等) | ・AI検索(Google AI Overview1 等) ・生成AI(Chat GPT 等) |
| 効果が期待できるライバル数 | ・約10サイト ※検索結果の1ページ目に採用 | ・1~5サイト ※採用される情報ソース数 |
| 何を成すべきか | ・検索結果で上位表示される ・クリックされる | ・AI検索の情報ソースとして採用される ・AIに正しい情報を届ける |
| 最終的な目標 | ・自社Webサイトへの来訪 | ・自社Webサイトへの来訪 ・お客様に正しい情報を届ける |
SEOの特徴
一般的に、SEOは、検索エンジンでの上位表示とクリック率を増やすための施策です。
その結果、自社Webサイトへの来訪数を増やすことで、見込顧客を増やすことを目的とします。
AIOの特徴
対して、AIOは、AI検索や生成AIが出力する結果内に、自社のサイトの情報を正しく出力するための施策です。
目的の一つは、SEOと同様で、自社Webサイトへの来訪数を増やすことです。
また、サイトに来訪しないユーザーに対して、正しい情報を提供することも目的となります。
生成AIの浸透と、Webサイト運営への影響
生成AI利用経験
※参照元:【総務省】情報通信白書令和7年版 インフォグラフィック
上のグラフは、個人の生成AI利用経験を年度別&国別に調べたものです。
日本では、2023年から2024年にかけて、個人の生成AI利用率は約3倍(9.1%⇒ 26.7%)になりました。
しかし、外国と比べるとまだまだ伸び幅があり、今後さらに生成AI利用は増えていく事が予測されます。



生成AI(AI検索)の利用率が上がると、Webサイトの運営にも影響が出てきます。
影響①:情報ソースとして採用されず、認知が減る
まず、SEOでは、検索結果に上位表示されるのがベストです。ただし、6~10位であっても、2ページ目以降であっても、サイト流入に繋がる可能性があり、SEOの価値はあります。
ところが、AI検索においては、情報ソースとして選ばれない限り、サイト流入に繋がりません。
影響②:AIの回答で満足し、Webサイトへの来訪が減る
そして、お客様がAI検索の回答で満足した際、サイトに行く必要がなくなります。
当然、サイトへの流入数が減少し、マーケティング視点では見込顧客数にも影響が考えられます。
影響③:誤った情報を配信してしまう可能性
さらに、生成AIは誤った情報を真実のように出力することがあります。(以下、ハルシネーション2)
たとえ、自社のWebサイト内に正しい情報を掲載していても、AIが正しく参照しなければ、誤った情報が配信されてしまう可能性があります。
もし、お客様が誤った情報を信じてしまえば、下記のようなリスクが考えられます。



ここが、Webサポート視点での超重要事項です。
- 新規顧客が、最新ではない正しくない情報をもとに商品・サービスを検討してしまう。
- 既存顧客が、誤った方法で商品・サービスを利用してしまう。
- 既存顧客が、誤った情報を基に、自社の商品・サービスから離反してしまう。
RAGはAI検索に対応出来るのか?
ここで、上述したハルシネーションの対策として、RAG3という技術があります。
RAGは、生成AIの情報ソースを限定することで、ハルシネーション(誤情報)を減らす技術です。
そのため、社内のヘルプデスクやコールセンター、Webサポート等で活用されつつあります。
Webサイト運営者は、自社サイト内のチャットボットに対しては、RAGを用いることが出来ます。
しかし、ユーザーが日常的に利用する検索ツール(ChatGPTやGoogle検索等)の結果に対して、RAGを適用させることは出来ません。



最近では、Webサイトに訪れず、生成AIやAI検索で調べ物を終了するケースが増えてきました。
このケースは、RAGでは対応できないため、AIOによる対策が必要となります。



それでは次の項から、AIO対策を紹介します。
AIO対策の基本
AIOにおいて、「これをするだけで完璧」という、明確で簡単な正解はありません。
統計データや有識者の経験則から、有効と思われる手法を試行錯誤することが多いです。
また、AIの評価基準も、逐次変わっていくと考えられるため、その手法も変化していきます。
今回は、現状有効な可能性が高いと考えられる手法を紹介します。
顧客目線で有用な情報を提供
まず、最も重要なことは、有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツを作成することです。
これについては、Googleが検索エンジンの仕組みについて解説しています。
たとえ今後、AIの評価基準が変化しても、おそらくこの点は変わらないと思います。
むしろ、AIの文章情報を読み取る能力が上がれば上がるほど、より重要視されると考えられます。


AIO対策①:Webサイトの構造化とAI対応
検索エンジンとAIに理解されやすい情報設計
AIはWeb上の情報をもとに回答を生成します。したがって、公式サイトの情報がAIに正しく読み取られるように設計することが重要です。
FAQ形式や手続きフローを明確に記述
生成AIが回答に使いやすいよう、FAQ形式や定義文などを整備します。
特に質問項目が大切で、自然言語で明確な質問と答えを記述すると有効です。
文章の主語・述語を明確にし、誤解の少ないわかりやすい表現で明記しましょう。



コールセンターでよく使われる「出来かねます」「致しかねます」等は、誤解を生みやすく、Webサイトに掲載する表現としては、オススメできません。
「出来る」「出来ない」を明確に表現することを推奨します。
ページタイトルや見出し(H1〜H3)を論理的に構成
Webサイトを構成するHTMLソースにおいて、ページタイトルや見出しを適切に構成します。
質問文をページタイトルに持っていく事で、AIに対して何の情報かを明示的に伝えることも出来ます。
メタディスクリプションに要点を簡潔に記載
さらに、Webページ毎に設定できるメタディスクリプション4には要点を簡潔に記載しましょう。
この方法は、一般的にSEOに効果があると言われてきました。
そして、AIはSEO効果が高いページの情報を好みやすいとも言われています。
そのため、AIO視点でも、メタディスクリプションの活用は有効であると思われます。
構造化データ(schema.org)の活用
検索エンジンやAIが情報を正確に理解するために、構造化データ(JSON-LD)を活用しましょう。
構造化データは「AIに正しく情報を伝えるための言語」とも言えます。
今後のAI時代において、企業が正確な情報を届けるための必須の仕組みとなるでしょう。



ちょっと複雑なので、下記にまとめています。
詳しくは、折りたたみ式の表示ボックスをクリックしてご覧ください。
Webサイトの情報をAIに正しく伝える「構造化データ」とは?
「構造化データ」とは、Webページの中で”これは何の情報か”を明確に示すための記述方法のことです。
たとえば、AIや検索エンジンは、ただの文章だけでは「これは商品の説明なのか?手続きの流れなのか?」を正確に判断できないことがあります。
そこで、構造化データを使うことで、次のように情報の意味を明示的に伝えることができます。
- 「これはよくある質問とその答えです」
- 「これはサービスの使い方をステップごとに説明しています」
- 「これは会社の連絡先情報です」
こうした情報を、AIが正しく理解できるようにすることで、検索結果やAIの回答に正確な内容が反映されやすくなります。
どんな場面で使うの?
構造化データは、以下のようなページに特に効果的です。
| ページの種類 | 構造化データの例 | 目的 |
|---|---|---|
| よくある質問(FAQ) | FAQPage | 質問と答えを明確に伝える |
| サービスの使い方 | HowTo | 手順をステップごとに示す |
| 商品・サービス紹介 | Product | 商品名・価格・特徴などを整理 |
| 会社情報 | Organization | 会社名・住所・連絡先などを明示 |
どうやって使うの?
Webページの裏側に、「JSON-LD」という形式でタグを埋め込むことで構造化データを設定します。
これはユーザーには見えませんが、検索エンジンやAIがページを読み取るときに使われます。
たとえば、FAQページならこんな感じです。
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [{
"@type": "Question",
"name": "サービスの申し込み方法は?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "公式サイトの申し込みフォームからご登録いただけます。"
}
}]
}このように記述することで、AIは「これは質問とその答えだ」と理解し、正確な情報を生成しやすくなります。
なぜ構造化データが重要なのか?
生成AIやAI検索は、Web上の情報をもとに回答を作ります。
構造化データを使うことで、AIが誤解せずに正しい情報を拾えるようになるため、ハルシネーション(誤情報)の防止につながります。
構造化データの導入方法
- Web制作会社や社内のWeb担当者に「構造化データを設定したい」と伝える。
- WordPressなどのCMS5を使っている場合、構造化データを簡単に追加できるプラグインもあります。
- Google Search Console6で構造化データのエラーや認識状況を確認できます。


E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化
E-E-A-T7とは、コンテンツの質と信頼度を評価するGoogleの指針です。
SEO効果にも繋がりますが、AIが信頼できる情報源として認識するための要素にもなり得ます。



基本的には 自社サービスのFAQページは、E-E-A-Tの観点をかなり網羅しやすい構成になっています。
さらに、以下のようなポイントを押さえることで、より確実にE-E-A-Tを満たしていると言えるようになります。
経験(Experience)
- 実際のユーザーの声や、社内での対応事例などをFAQに反映しているか?
- サービスを使った具体的なシナリオやユースケースが紹介されているか?
専門性(Expertise)
- 回答がサービス担当者や技術者など、専門知識を持つ人によって作成されているか?
- 専門用語の説明や、根拠のある情報が含まれているか?
権威性(Authoritativeness)
- 自社公式サイトであることが明示されているか?
- FAQページが他の信頼できるページ(会社概要、サポートページなど)と連携しているか?
信頼性(Trustworthiness)
- 情報が最新で、誤解を招かないように整理されているか?
- プライバシーやセキュリティに関する説明が明確か?
- 更新日や作成者情報が記載されているか?



FAQページは「ユーザーの疑問に対して、正確で誠実な回答を提供する場」なので、ユーザー中心の設計がされていれば、自然とE-E-A-Tの要件を満たしやすくなります。
AIO対策② AI検索・生成AIへの情報提供
Google Search Consoleの活用
Google AI Overviewは検索結果をベースにしているため、検索順位の改善がAI回答の精度向上に直結します。
Google Search Consoleでは、Webサイトの構成を検索エンジンに伝えることが可能です。
その上で、適正な構成になっているか、様々な指標で指摘されることも出来るため、検索順位の改善にも繋がります。
- サイトマップの送信
- インデックス状況の確認と改善
- ページの更新頻度を高める
外部の信頼性あるサイトに情報を掲載
ChatGPTなどは、信頼性の高い外部サイト(例:Wikipedia、ニュースサイト、業界メディア)の情報を優先する傾向があります。
- Wikipediaに自社ページを作成(編集方針に注意)
- 業界メディアに寄稿・掲載依頼
- プレスリリースをPR TIMESなどに掲載
SNSでの情報発信
AI検索は、WebサイトだけではなくSNSの情報も参照します。
そのため、公式な情報をSNSに記載したり、SNS上でWebサイトのFAQページを紹介することも有効です。
AIO対策③:誤情報の拡散防止
古い情報の更新・削除
ネット上に残る古い情報や非公式な記述がAIに学習されてしまうことがあります。
公式サイトやSNSでの訂正・誘導を積極的に行いましょう。
Q&AサイトやSNSでの対応
誤情報が拡散されている場合は、公式アカウントでの回答やリンク誘導が有効です。
まとめ:正確な情報発信のために今すぐできること
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 顧客目線の情報 | ・顧客目線で有用な情報を提供 |
| Web構造化 | ・FAQ形式や手続きフローを明確に記述 ・タイトルやメタディスクリプションの整備 ・構造化データの活用 ・E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化 |
| AI対応 | ・Google Search Console の活用 ・外部の信頼性あるサイトに情報を掲載 ・SNSでの情報発信 |
| 誤情報対策 | ・古い情報の更新・削除 ・Q&AサイトやSNSでの対応 |
おわりに
生成AIの普及により、企業の情報発信は新たなフェーズに入りました。
正確な情報をAIに届けることは、ユーザーとの信頼関係を築く第一歩です。
今後もAI時代に対応した情報設計を進めていきましょう。
脚注
- Google AI Overview:検索クエリに対してAIが複数の情報源を統合・要約し、検索結果の上部に表示する機能。 ↩︎
- ハルシネーション:生成AIが事実と異なる情報を生成してしまう現象。 ⇒ ハルシネーションとは ↩︎
- RAG(Retrieval-Augmented Generation):生成AIが回答を作成する際に、特定の情報を参照してから文章を生成する手法。 ⇒ RAGとは ↩︎
- メタディスクリプション:検索結果のページタイトルの下に表示される、Webページの内容を簡潔に説明した文章。SEO対策とクリック率の向上に重要。 ↩︎
- CMS:コンテンツマネジメントシステムの略。Webサイトをノーコードで作成できるツール。
⇒ 代表例:WordPress ↩︎ - Google Search Console:Google検索結果におけるウェブサイトの表示状況やパフォーマンスを把握・改善するための無料の分析ツール ⇒ Google Search Console ↩︎
- E-E-A-T:経験・専門性・権威性・信頼性に基づいて、コンテンツの質と信頼度を評価するGoogleの指針
⇒ 品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加 / Google 検索セントラル ↩︎
